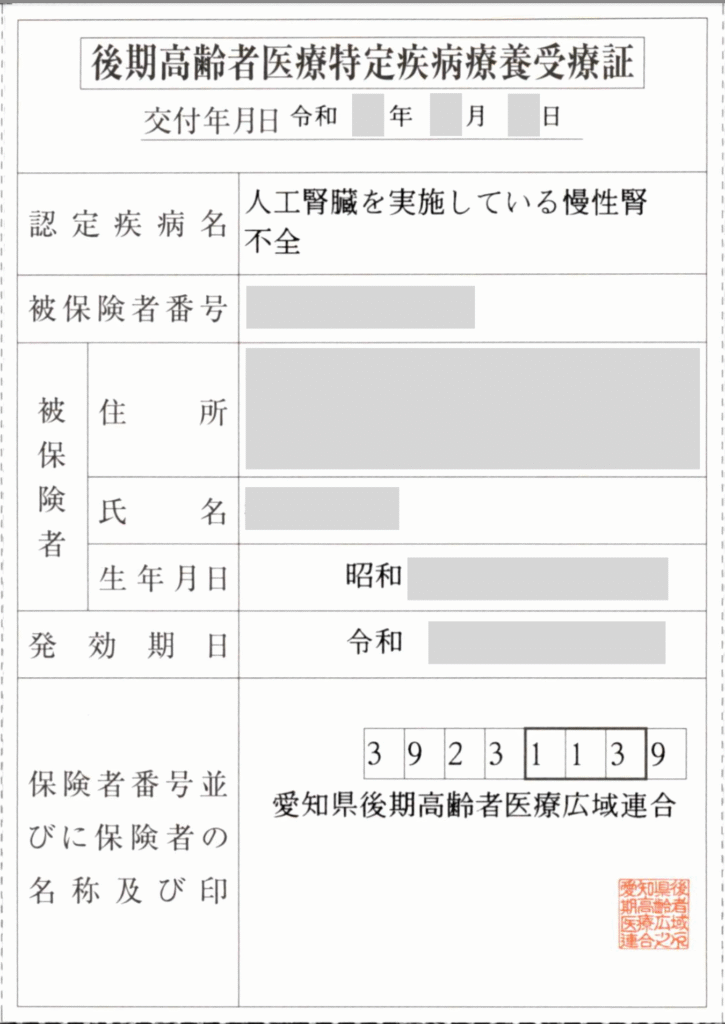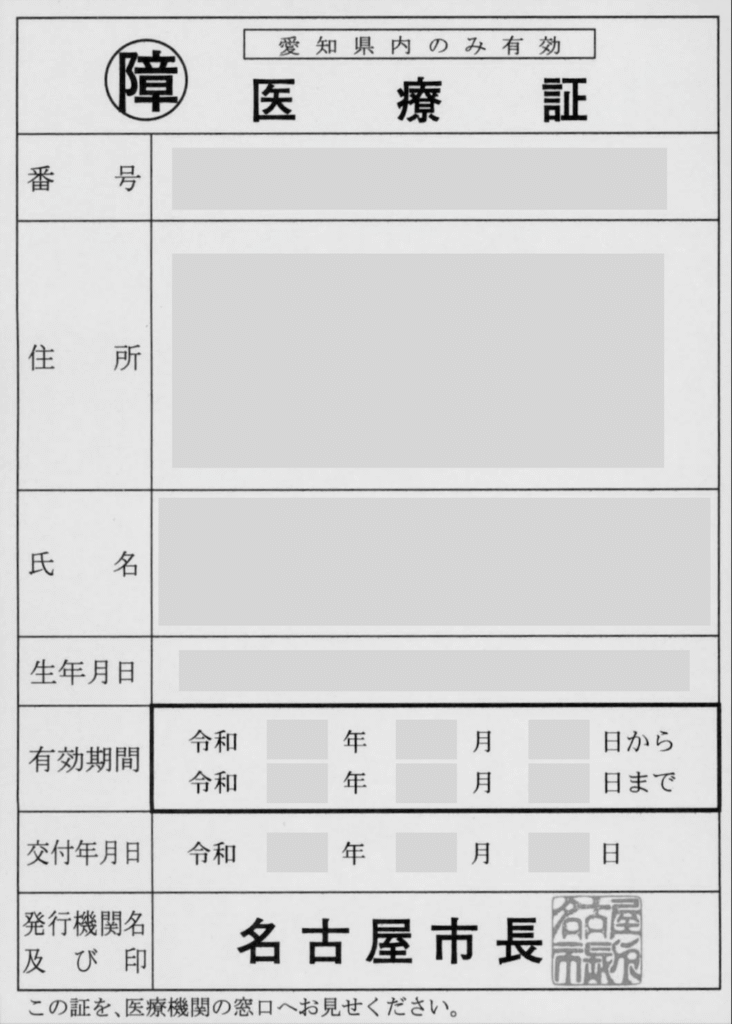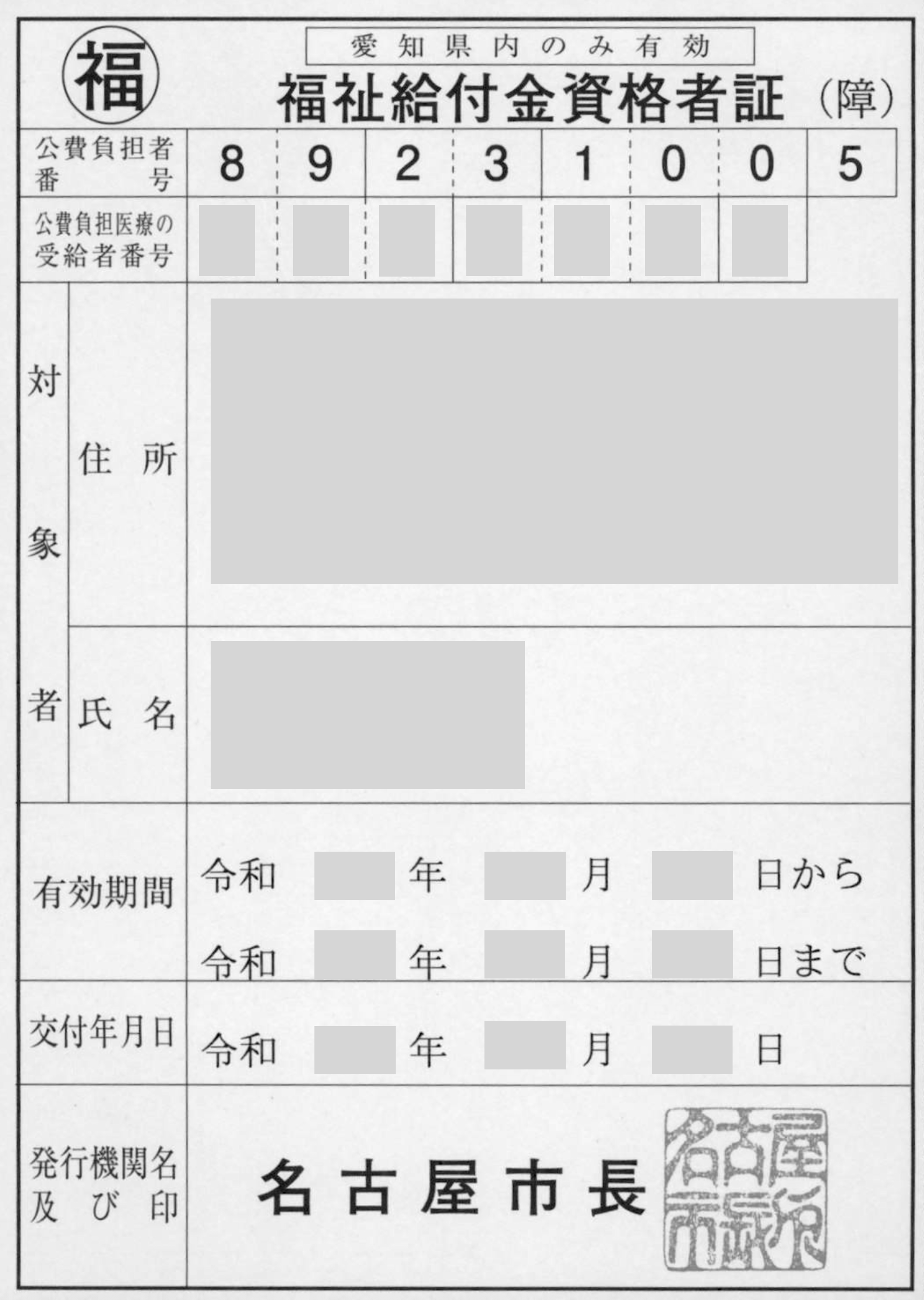PTAの説明文書
用語説明
縫合(ほうごう):縫い合わせること
吻合(ふんごう):管と管を縫合してつなぎ合わせること
狭窄(きょうさく):細く、狭くなること
閉塞(へいそく):血管が詰まってしまい、血液の流れが止まってしまうこと
シャントの血管内治療
シャント治療には「外科手術」と「血管内治療」とがあります。外科手術とは皮膚を切開して行う治療です。血管を縫合、吻合するためには外科手術が必要です。血管内治療は、「経皮的治療」とも言い、太さ約2mmのプラスチックチューブ(シース)をシャント血管に刺して、血管の内側から治療をする方法です。
血管内治療の代表格は血管が細くなった部分を風船でひろげる「PTA」です。
PTA(経皮的シャント拡張術)
シャント血管が狭窄すると、透析で十分な血液がとれなくなったり、シャントが閉塞してしまう原因になります。そのため、狭窄した血管をひろげるために、バルーンカテーテルで狭窄した部位を加圧し、血管を内側から拡張します。PTAはエコーを見ながら行う場合と、X線透視を使用する場合があります。治療にかかる時間は15-30分程度のことが多いですが、病変が複雑な時などは1時間以上かかることもあります。
PTAで起きる合併症には再狭窄、破裂、シース部の血腫などがあります。
麻酔
当院で行うシャント治療はすべて局所麻酔と神経ブロックで行っています。局所麻酔は治療をする部位に直接麻酔薬を注射する方法です。神経ブロックは治療をする部位の感覚をつかさどる神経へ麻酔薬を注射する方法です。
麻酔に関連する合併症には局所麻酔薬に対するアレルギー、大量の局所麻
酔が吸収されることよる急性中毒、麻酔薬の注入による神経、血管損傷などがあります。
血管内治療の危険性、合併症
再狭窄
シャント狭窄にPTAを行っても残念ながら数ヶ月のうちに60~70%で再狭窄が生じます。
破裂
バルーン拡張によって血管が破れてしまうことがあります。血管が破れると周囲に出血をしますが、ほとんどの場合、出血した血液がかたまることにより止血されます。出血は数週以内に吸収されます。出血が
止まらないときには「ステントグラフト」(シースから入れられる人工血管の一種)を使用したり、緊急外科手術が必要になることもあります。私が勤務していた施設では2020年に6309件のPTAを行い、破裂部分が止血できず、外科手術が必要になったのは4件(0.06%)でした。
放射線被曝(ひばく)
血管内治療はエコー下またはX線透視下に行います。X線透視下における血管内治療では、X線による被爆を伴います。当院では、おおよそ1分間に0.5~8mGyのX線を使用して治療を行っています。(医療被爆ガイドラインで定められた被爆低減目標値は1分間に20mGyです。
血管攣縮(れんしゅく、スパスム)と治療直後の閉塞
PTAや注射針を刺す刺激によって血管の筋肉が収縮し、血管が縮み上がり、血流が止まってしまう場合があります。通常は1時間以内に筋肉がゆるみ元に戻りますが、血液がかたまり、シャントを閉塞させてしまうこともあり、再治療、再手術が必要になることもあります。
□治療中に治療内容を変更する場合があります
治療の状況により、はじめに予定していた方法を変更する場合があります。治療の途中で新たな病変が判明したり、合併症に対処したりするためです。治療内容の変更は医師が必要と認めた時には治療中に患者本人、付き添いのかたに説明することもありますが、通常は治療を終えた後に変更内容を説明します。